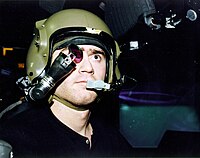拡張現実
|
Read other articles:

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: Donat kampung – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTORArtikel ini berisi konten yang ditulis dengan gaya sebuah iklan. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menghapus konten yang dianggap sebagai sp…

Roller coaster at Six Flags America The Joker's JinxA train exits the Cobra RollSix Flags AmericaLocationSix Flags AmericaPark sectionGotham CityCoordinates38°54′36″N 76°46′34″W / 38.910°N 76.776°W / 38.910; -76.776StatusOperatingOpening dateMay 8, 1999Cost$10 million[1]General statisticsTypeSteel – LaunchedManufacturerPremier RidesDesignerWerner StengelModelLIM CoasterLift/launch systemLIM launchHeight78.8 ft (24.0 m)Length2,705 …

Nokia 6290 adalah produk telepon genggam yang dirilis oleh perusahaan Nokia. Telepon genggam ini memiliki dimensi 94 x 50 x 20.8 mm dengan berat 115 gram. Diumumkan pertama kali kepada publik pada November 2006. Fitur Kamera digital 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash Kamera depan SMS MMS Email Instant Messaging Visual radio Slot kartu microSD hingga 4GB Jaringan 3G 384 kbps Permainan Radio FM Internet v2.0 miniUSB Inframerah Bluetooth v2.0 WMV/RV/MP4/3GP video player MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A m…

نادي اتحاد مانشستر تأسس عام 2005 الملعب غيغ لين البلد المملكة المتحدة الدوري دوري الشمال الممتاز [لغات أخرى] الموقع الرسمي الموقع الرسمي الطقم الرسمي الطقم الأساسي الطقم الاحتياطي الطقم الثالث تعديل مصدري - تعديل نادي اتحاد مانشستر لكرة القدم (با…

Ini adalah artikel tentang buah-buahan. Untuk grup musik lihat Yuzu (grup musik) Yuzu Buah yuzu di pohon Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Divisi: Magnoliophyta Kelas: Magnoliopsida Subkelas: Rosidae Ordo: Sapindales Famili: Rutaceae Genus: Citrus Spesies: C. ichangensis x C. reticulata var. austera Nama binomial Citrus ichangensis x Citrus reticulata var. austera Yuzu atau (Citrus ichangensis x C. reticulata, sebelumnya C. junos Siebold ex. Tanaka; bahasa Jepang ユズ, 柚, 柚子 (yuz…

العلاقات السلوفينية الناوروية سلوفينيا ناورو سلوفينيا ناورو تعديل مصدري - تعديل العلاقات السلوفينية الناوروية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين سلوفينيا وناورو.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه المقا…

American baseball player (born 1979) This article is about the Major League baseball pitcher. For other uses, see Aaron Cook (disambiguation). Baseball player Aaron CookPitcherBorn: (1979-02-08) February 8, 1979 (age 45)Fort Campbell, Kentucky, U.S.Batted: RightThrew: RightMLB debutAugust 10, 2002, for the Colorado RockiesLast MLB appearanceSeptember 28, 2012, for the Boston Red SoxMLB statisticsWin–loss record76–79Earned run average4.60Strikeouts578 Teams …

American actor (1941–2021) For the Australian rugby league player, see Tommy Kirk (rugby league). Tommy KirkKirk on the set of Son of FlubberBornThomas Lee Kirk(1941-12-10)December 10, 1941Louisville, Kentucky, U.S.DiedSeptember 28, 2021(2021-09-28) (aged 79) (date body found)Las Vegas, Nevada, U.S.OccupationActorYears active1953–1975, 1987-2001Known forThe Shaggy DogSwiss Family RobinsonThe Absent-Minded ProfessorOld YellerParent(s)Louis and Lucy Kirk Thomas Lee Kirk (Decembe…

Railroad museum in Sacramento, California California State Railroad MuseumRailroad Museum exteriorShow map of CaliforniaShow map of the United StatesLocation111 I Street, Sacramento, CaliforniaCoordinates38°35′5″N 121°30′16″W / 38.58472°N 121.50444°W / 38.58472; -121.50444Established1981Governing bodyCalifornia Department of Parks and RecreationWebsitehttps://www.californiarailroad.museum/ The California State Railroad Museum is a museum in the California…

Jeremy NorthamNortham pada 2010LahirJeremy Philip Northam1 Desember 1961 (umur 62)Cambridge, Cambridgeshire, InggrisAlmamaterBedford College, London (Sarjana, 1984)Bristol Old Vic Theatre SchoolPekerjaanPemeranTahun aktif1987–sekarangSuami/istriLiz Moro (m. 2005; bercerai 2009?)Orang tuaJohn NorthamRachel Howard Jeremy Philip Northam (lahir 1 Desember 1961) adalah seorang pemeran asal Inggris. Usai sejumlah peran televisi, ia meraih perhatian saat memerankan Mr. Knightley dalam adapt…

American alternative rock band Not to be confused with the car Plymouth Reliant K. Relient KRelient K performing in May 2007. From left to right: Jon Schneck, Matt Hoopes, Matt Thiessen, Dave Douglas and John Warne.Background informationOriginCanton, Ohio, U.S.GenresAlternative rock[1] · Christian alternative rock[2] · pop-punk[3]Years active1998–presentLabels Gotee Capitol Mono vs Stereo Jive RCA Members Matt Hoopes Matt Thiessen Dave Douglas Jon Schneck Ethan Luck P…

La Trimouillecomune La Trimouille – Veduta LocalizzazioneStato Francia Regione Nuova Aquitania Dipartimento Vienne ArrondissementMontmorillon CantoneMontmorillon TerritorioCoordinate46°28′N 1°03′E / 46.466667°N 1.05°E46.466667; 1.05 (La Trimouille)Coordinate: 46°28′N 1°03′E / 46.466667°N 1.05°E46.466667; 1.05 (La Trimouille) Superficie41,85 km² Abitanti989[1] (2009) Densità23,63 ab./km² Altre informazioniCod. pos…

Loganatha Perumal TempleReligionAffiliationHinduismDistrictNagapatnamDeityLoganathar (Vishnu) Aravindavalli (Lakshmi) Damodara Narayanan (Vishnu) Loganayaki (Lakshmi)FeaturesTower: UtpalaTemple tank: SravanaLocationLocationThirukannagudi, SikkalStateTamil NaduCountryIndiaLocation in Tamil NaduGeographic coordinates10°45′23.7″N 79°45′48.7″E / 10.756583°N 79.763528°E / 10.756583; 79.763528ArchitectureTypeDravidian architectureElevation33 m (108 ft)Hind…

1960 song written by Sid Tepper and Roy C. Bennet Catch MeSingle by Cliff Richard and the Shadowsfrom the album 21 Today B-side'D' in Love (US)Tough Enough (Australia)ReleasedJanuary 1961 (US)April 1962 (Australia)Recorded9 September 1960[1]StudioEMI Studios, LondonGenrePopLength2:22LabelABC-ParamountColumbiaSongwriter(s) Sid Tepper Roy C. Bennett Producer(s)Norrie ParamorCliff Richard and the Shadows singles chronology I Love You (1960) Catch Me (1961) Theme for a Dream (1961) Catch Me …

2016年美國總統選舉 ← 2012 2016年11月8日 2020 → 538個選舉人團席位獲勝需270票民意調查投票率55.7%[1][2] ▲ 0.8 % 获提名人 唐納·川普 希拉莉·克林頓 政党 共和黨 民主党 家鄉州 紐約州 紐約州 竞选搭档 迈克·彭斯 蒂姆·凱恩 选举人票 304[3][4][註 1] 227[5] 胜出州/省 30 + 緬-2 20 + DC 民選得票 62,984,828[6] 65,853,514[6] 得…

School district in Pennsylvania Hempfield School DistrictLocationPA United StatesDistrict informationTypeSchoolStudents and staffStudents6800+Teachers500+Other informationWebsiteHempfield School District Hempfield School District is a school district of 6800+ students educated in 10 schools by 500+ teachers in Lancaster County, Pennsylvania.[1] It is a member of Lancaster-Lebanon Intermediate Unit (IU) 13. References ^ Hempfield School District statistics External links Official website …

Type of legal instrument in Common law For other uses, see Deed (disambiguation). Look up deed in Wiktionary, the free dictionary. Property law Part of the common law series Types Personal property Community property Real property Unowned property Acquisition Gift Adverse possession Deed Conquest Discovery Accession Lost, mislaid, and abandoned property Treasure trove Bailment License Alienation Estates in land Allodial title Fee simple Fee tail Life estate Defeasible estate Future interest rema…

Pascual JordanPascual Jordan pada tahun 1920-anLahir18 Oktober 1902Hanover, Kerajaan Prussia, Kekaisaran JermanMeninggal31 Juli 1980(1980-07-31) (umur 77)Hamburg, Jerman BaratKebangsaanJermanDikenal atasMekanika kuantum, teori medan kuantum, mekanika matriks, aljabar JordanPenghargaanMedali Max Planck (1942), Medali Carl Friedrich Gauß (1955)Karier ilmiahBidangFisika teoriInstitusiUniversitas Teknik Hanover Universitas GöttingenPembimbing doktoralMax BornMahasiswa doktoralJürgen Ehlers, …

London CallingCoronation of Queen Elizabeth II issueCategoriesListings magazineFrequencyMonthlyFinal issueDecember 2004CompanyBBC World ServiceCountryUnited KingdomBased inLondonLanguageEnglishOCLC4652734 London Calling (later renamed BBC Worldwide, then BBC On Air) was a monthly magazine[1] that contained programme listings for the BBC World Service shortwave radio broadcasting service. Originally called the Empire Programme Pamphlet (for what was then known as the BBC Empire Service) a…

This article is part of a series onBanking in theRussian Federation Central Bank of Russia Monetary policy Regulation Lending Credit card Deposit accounts Current Time deposit Savings Account insurance Deposit Insurance Agency Payment & Transfer Electronic funds transfer (EFT) Debit card Wire transfer System of Fast Payments Bill payment Types of credit organizations Bank Settlement NBCO Payment NBCO NBDCO NBCO - central counterparty Biggest commercial banks[1] Sberbank VTB Gazpromba…